
カモンアップ社長・永瀬 泰子(ながせ やすこ)独占インタビュー パート⑤
2020-04-04
こんばんは!創立17年、国際シェアハウスの草分け「カモンアップ」代表の永瀬泰子です。まだ日本にシェアハウスという文化が耳慣れなかった2006年。どのような道筋で起業に至ったのか、マイストーリーの第5回目です。
永瀬社長は、渋谷区の青年会議所のメンバー等いくつもの顔があります。それらの活動が少なからず、カモンアップの道のりに影響を及ぼしてきました。

男性不妊啓発のためのキャンペーンイベント開催
青年会議所(JC)とは、若手経営者が任意で参加して、ボランティアや子どもの育成事業などの社会貢献活動を行う団体で、日本全国に支所があります。 他のメンバーとの交流を通して会社経営のノウハウを共有したり、お互いに励まし合い切磋琢磨し合えたりする、私にとって精神的な拠り所の一つでもありました。 私がここで企画した事業のうち、特に思い入れのある2つについてお話ししましょう。
ひとつは、不妊治療に関するキャンペーンイベント。 不妊は、女性側の問題として受け取られがちで、女性だけが病院に通うケースが多いのですが、実は、「無精子症」など男性側に原因がある場合も少なくありません。 この「男性不妊」について多くの人に啓発するため、無精子症の治療経験のある、ミュージシャンのダイヤモンド・ユカイさんを招いてフォーラムを開く企画を立ち上げました。 後援として渋谷区、スポンサーは株式会社TENGAさんにお願いすることにしました。 「TENGA」というと、アダルトグッズの企画販売で有名ですが、実は「性をもっとオープンに健全に考えよう」という啓発活動に真摯に取り組んでいる会社でもあります。「男性不妊のキャンペーンとコラボしたら面白いし、多くの人の注目を集められるに違いない」と思い、同社に白羽の矢を立てたのです。 会場として、その頃オープンしたばかりの「渋谷ヒカリエ」はどうかと、東急に話を持ち込むと、「面白そうですね!」と好感触。これはいけるぞと思いました。
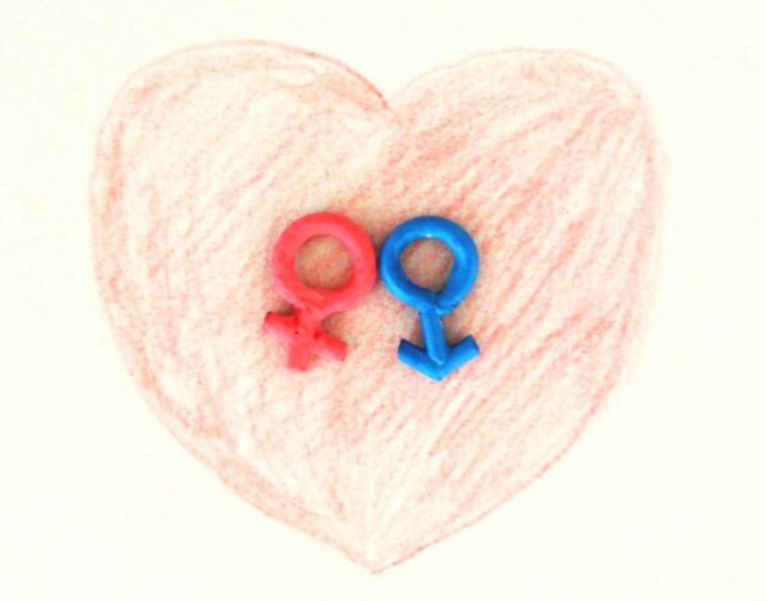
「勘違いしているんじゃないですか?!」渋谷区長の机を叩く
ところが、開催1週間前。 突然、東急から
「ヒカリエが使えないかもしれません」
との電話が。 一体、どういうこと? 理由を聞いてびっくり。なんと、渋谷区長が「TENGAと渋谷区を並ばせるわけにはいかない」と、私を通さず東急社長に直接連絡したらしいのです。 信じられない!いきり立って、私は「5分でいいから話をさせてくれ」と渋谷区長室に乗り込み、区長の机をバンと叩き、こう言いました。
「勘違いされてませんか?もう一回ちゃんと企画書を見てください。」 ことの次第をTENGAさんに連絡したところ、怒られるかと思いきや、意外にも
「そうですよね。ここで渋谷区と波風を立てれば、先々問題になって、私たちもやりづらくなります。それは避けたいので、どうか丸く納めてください」
という腰の低い姿勢。 この対応には驚きました。彼らは自分たちの立場のことをよくわかっているのです。さすがだなと思いました。 開催を目前に控えても、渋谷区長の見解は結局、変わらず。 でも、せっかくこの日のために一生懸命準備してきたイベントを中止したりしたくないし、TENGAさんや東急さんのせっかくの厚意をふいにしたくない… 結果、どうしたか。 私たちは、悩んだ末「後援・渋谷区」の文字をプログラムから削除して、計画通りにイベントを開催することにしました。 苦渋の決断でしたが、イベントは大盛況に終わりました。 TENGAと東急、真剣に社会問題と向き合う二社を仲立ちしてイベントを成功させることができた。このことは私の大きな自信になりました。

3・11をきっかけに国連子ども大使の派遣活動へ
もう一つ、思い出に残っているのは、子どもたちを国連本部に派遣して、飢餓や貧困などに苦しむ人たちの現状を知ってもらう「少年少女国連大使」の派遣活動です。 事業を立ち上げたきっかけは、あの東日本大震災でした。 その頃私は、海外の貧しい国に向けての支援事業を担当していたのですが、震災のニュースを聞いて「今は海外のことをやっている場合じゃない!」と、それらの活動をすべて投げ打って、すぐに救援ボランティアをしに東北の被災地へと駆けつけました。 現地へ行ってみて驚いたのは、マラリアで自国民が苦しんでいるような極貧国からすらも支援が送られてきたこと。 世界中の人たちが日本の窮状を見て、心配してくれている。心が熱くなりました。 「今こそ、日本人に世界とのつながりをもっとしっかり感じてほしい。そのために、自分に一体何ができるだろう…?」 私は猛然と考え始めました。
蘇る「人形交換大使」
そこでハッと思い出したのが、私自身が8歳の頃に「人形交換大使」という交換留学制度でアメリカに渡った時のこと。 この制度は、日米間で相互に子どもたちを派遣して、自国の人形を交換し合うことで両国の平和・友好を祈念するというもの。もともとは戦前に始まった制度でした。 ところが、第二次世界大戦を機に、贈られた人形は
「敵国のものだから」
ということでほとんどが燃やされてしまいます。 そんな中、心ある一部の人たちが
「人形には罪はない。子どもたちの心は本物だ」
と人形を大切に隠し持っていてくれていたことで、戦後、それらの人形を修復して日米間でもう一度交換しようという、人形交換大使のリバイバル活動につながりました。 私は、その大使のひとりとしてアメリカに渡ったのでした。 広い世界を垣間見て「将来、世界の架け橋になりたい」と願ったことを、今でもよく覚えています。
小さな国連大使たちの勇姿
「あの時私が見たように、多くの子どもたちに広い世界を見せたい。人形交換大使にあやかったプログラムが何かできないか」
…ということで立ち上げたのが「少年少女国連大使」でした。 全国各地の代表として派遣する「子ども大使」たちにはミッションをもうけました。アメリカからの帰国後、例えば先生やみんなの前で話すとか、地元のテレビ局や新聞、ラジオで取り上げてもらうなどして、現地で経験し学んだことを広めてもらうのです。 初年度は10人の子どもたちを派遣しました。帰国した子どもたちは見事にミッションをはたし、その声はメディアを介して何万人もの人に届き、反響を呼びました。 この試みが評価されて、以降、少年少女国連大使事業は毎年続いており、今年で9年目になります。現在、都道府県ごとに毎年一人ずつ、合計30人が派遣されています。

次回、第6回目のインタビューはいよいよ最終回です。カモンアップのこれからの展望や社長の夢について、お話を伺います!
多様性を楽しみ、ゆったり暮らす。
シェアハウスならカモンアップ

©2022 Come on up inc.
